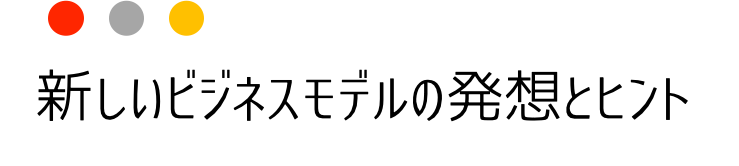プロフィール

「新しいビジネスモデルの発想とヒント」運営管理
「儲けのしくみ」著者
フィナンシャル・ノート代表 酒井 威津善(さかい いつよし)
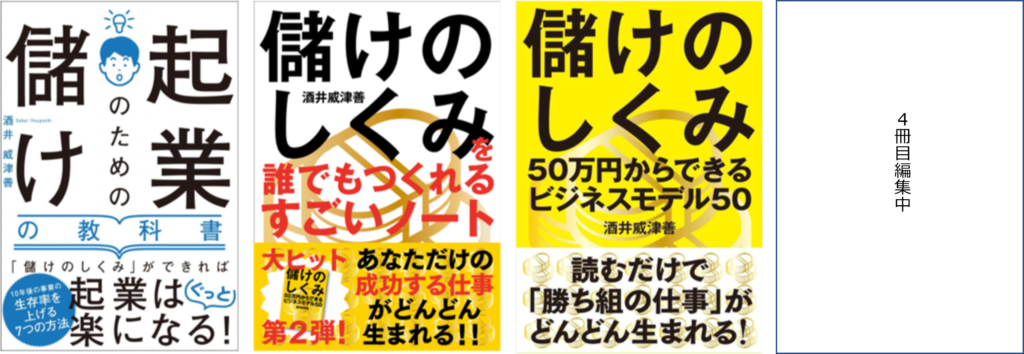
サマリー
TIS株式会社にて10年間システム開発企画に従事。損保会社、リサイクルショップなど上場、上場準備中の企業を中心に独自企画を持ち込み、東京・大阪本社で営業トップに。
創業わずか7年でマザーズ上場を果たしたクライアントに触発され、財務に転進。ミドルステージの不動産、住宅、遊技機メーカーなどで計12年間CFOに従事。上場準備や財務基盤構築などを手掛ける一方、法規改正などの影響を受け、2社で倒産の憂き目に会う。
40億円以上のリスケと新規事業立ち上げを推進していく中、資金だけでは企業を救えないことを痛感。常に新しいビジネスを生み出し続けることが最重要と考え、TIS時代のコンセプトスタイルをベースに独自の発想方法を研究、実践。
現在は、「パーツアレンジ式発想法」をコンセプトに、地方自治体や法人向けのセミナー、新規事業創出ワークショップ、起業予定者向けの個別コンサルティングなどを行っている。「儲けのしくみ(自由国民社)」など新しいビジネス発想に関する書籍を3冊上梓。2024年に4、5冊目を出版予定のほか、アイデア発想を求める人、企業に情報発信を続けている。
経歴サマリー
1.1991年04月~2002年10月(11年7ヶ月)TIS株式会社
企業概要 法人企業向けシステムインテグレータ
部署名 産業事業本部
役割 システム開発の企画提案
2.2002年11月~2008年08月(5年10ヶ月) アプトホーム株式会社
企業概要 個人向けオーダー型住宅設計販売
部署名 管理本部
役割 株式公開準備室室長代理兼財務部長
公開準備及び資金調達および新規事業立ち上げ
3.2008年09月~2016年8月(8年0ヶ月)株式会社JPS
企業概要 遊技機の企画設計製造
部署名 管理本部 財務部
役職 執行役員 財務部部長
遊技機(パチスロ)開発資金調達および財務管理
4.2016年09月~ 現在(4年4ヶ月) フィナンシャル・ノート
代表
中堅企業~フリーランスまでの新規事業の創出・設計サポート&財務コンサルティング
経歴詳細
1.1991年04月~2002年10月(11年7ヶ月)TIS株式会社
法人向けシステム開発の企画・提案に従事。
当該業務遂行にかかる目標達成に向け、以下の2つの戦略で取り組む。
1)特定カテゴリーに集約した営業戦略
新規システム需要の高い「FC」と資金余力の高い「高級ブランド」にフォーカスを当て、営業工数を集中的に投下。FC向けの開拓戦術では、事業開発を主力とするコンサルティング企業と連携し、経営要件部分(最上流部分)とシステム要件部分で住み分けを行い、機会増大を促進。
業務システム開発費用のうち、フランチャイザー向けに本部分の課金をイニシャルで負担、フランチャイジー分を展開店舗数による配賦課金方法を運用。
これにより、「古本市場」「ホリデースポーツクラブ」「スーパースーツファクトリー」など、上場前のFC系企業にて開発及びデータセンター運用を受注。
海外高級ブランド向けのアプローチでは、世界的ブランドであるエルメスジャポンの受注をトリガーとして、実績を横展開。グッチ、ルイ・ヴィトン、ゴディバなどを受注に成功。
2)RFPベースコンペを回避する「ファームウェア」型提案
富士火災海上保険、日産ディーゼル工業、電子航法研究所とのコラボレーションによる新保険商品の開発や、東日本ハウス、リコー、ソニーとのコラボレーションによる建築現場入退出管理システムなどを企画し、RFPベースによる競合生成を事前回避することに成功。(システム開発費用は必要分を企画予算内に組み込み、受注。従来からの「発注企業」-「受注企業」の枠組みを外す)
2.2002年11月~2008年08月(5年10ヶ月)アプトホーム株式会社
財務責任者として株式上場準備と財務の立て直し及び付随する新規事業立ち上げに5年間従事。当初、上場準備の遂行を行っていたが、建築基準法の厳格化に伴い、財務基盤の再構築に変更。事業再構築では、以下3つの論点でアプローチ。
a.総資産の圧縮
稼働前のものを中心に販売用及び自社拠点用土地について、任意売却、銀行経由等により4割を売却。併せてプロパンガス事業売却による非共通コストの削減を実現。
b.コスト集約とモデルチェンジ
全国の拠点を関東圏に集約し、広告費、人件費などを27%以上削減。各拠点に併設されていた住宅展示場をロードサイドにあるショッピングセンターへ隣接させ、販管費圧縮を図るとともに、販売機会の向上を実現。
c.新規顧客獲得施策の実施
展示場の資産回転率向上を目的として、1泊2日の居住体験ツアー(有償)を実施。購入検討家族向けに実際に泊まってもらうことで、口コミ狙いと契約の促進を図った
事業再構築と併行し、
・みずほ銀行協調融資(6億円、3年償還、利率2.5%)
・静岡銀行、みずほ銀行、りそな銀行無担保私募債3件の発行(各3年償還、2億円)などの資金調達を行う。
結果として、月次での現金及び現金同等物の残金を平均で4,000万円/月程度で安定させることに成功。
3.2008年09月~2016年8月(8年0ヶ月)株式会社JPS
パチスロ開発用の資金調達及び管理本部における財務管理全般に従事。
金融機関からの間接金融と併行して、新規事業に紐づけた直接金融のしくみを構築、運用。資金使途を設備として、一般的な借り入れ(手形、証書貸付、マル保付、預担等)による長短での借り入れ及びリファイナンスを実行。また、新規事業として、イニシャルコストゼロで設置した中古機による月次単位での収益を折半する(ホール側と折半)事業を運用、展開。→ 匿名組合を設立し、中古機の運用収益を毎月分配。ホール側メリット:イニシャルコスト0。自社メリット:開発コスト0。投資家:平均的金融商品以上の利回り。その他、新機種開発用に「私募債(銀行引受ではない)」の起債と、償還にかかる管理を行った。
4.2016年09月~現在(4年4ヶ月)フィナンシャル・ノート
1)新規事業の創出及び設計
「ローラー作成型発想法」によるビジネスモデル案の創出プログラムの提供。高等学校などで運用されている「アクティブ・ラーニング」を応用し、チーム単位でアイデアの創出を図る。従来のアイデア創出とは異なり、業界慣習、知見やスキルを乗り越えた、非属人的アイデアの創出が可能。
(実績)
・倉庫運送業におけるアスリート監修の健康促進型レストラン
・印刷業におけるクラウド型印刷サイト
・サブスクリプション型コーヒーショップ
・完全成功報酬型出版コンサルティング
2)財務コンサルティング
改善指標をFCF(フリーキャッシュフロー)にとして、「システム開発」と「ファイナンス」の知見による以下の手順を運用。
①現況ヒアリング及び概略要件の抽出
②ステアリングコミッティの設置
③表出する諸問題と各群諸要素との再接続、及び原因抽出にかかるイシューの洗い出し
④B/S(貸借対照表)ベースでの目標設定
⑤WBS項目抽出と選定(デッドライン)
⑥週・四半期単位でのアクティビティ・レビュー
以下の業種において、中央値で122%のFCF改善
・美容室チェーン
・運送業
・ドローン開発企業
・航空部品開発企業
・建設業
・求人広告企業
・協同組合
3)執筆活動
「新規事業」をキーワードとして、執筆活動を行なう。書籍、コラム、自社サイトにおいて、グランド・セオリー的要素を排し、実務レベルで有効性のあるコンテンツを提供。書籍出版合計6万5千部、ブログのグーグル検索結果3位などの結果を得た。
書籍: ※すべて商業出版
・儲けのしくみ 50万円からできるビジネスモデル50(自由国民社)
・儲けのしくみを誰でもつくれるすごいノート(自由国民社)
・起業のための儲けの教科書(ソシム)
※2024年1月現在、4冊目、5冊目を執筆中。
WEBサイト:
新しいビジネスモデルの発見とヒント http//:www.financial-note.com/
ウェブマガジン:
「儲けの視点」 ~成功は“切り口”が10割 https://foomii.com/00278